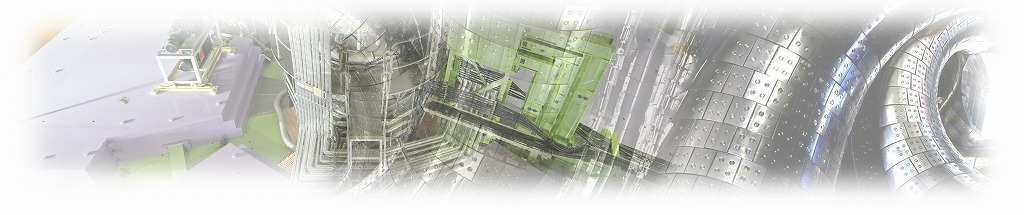核融合(フュージョンエネルギー)は資源が偏在しないエネルギー源として、その実現が期待され、1960年代から開発が進められてきた。近年は、温室効果ガスによる地球温暖化の懸念とスタートアップ企業などによる民間資本の参画により、その開発が加速される期待が高まっている。本公演では、フュージョンエネルギーの実現に向けたこれまでの歩みと課題について解説する。
重イオン加速器は原子核物理学、ビーム育種、ラジオアイソトープ(RI)製造などさまざまな目的に使われてきた。近年、短寿命のRIを加速期で人工的に作って、元素の起源や宇宙の進化を調べる研究が盛んになっており、この目的のための大規模な加速器施設が世界各国で稼働あるいは建設されている。この講義では、理研RIIビームファクトリーの加速器を例にとり、重イオン加速器の特徴と現状、および将来の課題について論じたい。
負イオン源は、負電荷を持つイオンビームをプラズマから引き出す装置であり、主として核融合加熱分野や大強度陽子加速器(素粒子実験、物質・生命学実験など)、あるいはタンデム加速器などで活用される。本特別講義では、負イオン生成の原理とイオン源の構造、また高エネルギー&大強度ビームを生成するための負イオンの利点について説明する。さらに、負イオン源の実践例としてJ-PARC陽子加速器における粒子源の状況と、ビーム性能向上に向けた負イオンビーム分野の課題を紹介する。
自己燃焼核融合プラズマを実現するための外部プラズマ加熱・電流駆動装置である中性粒子ビーム入射装置について、要求される性能およびシステム全容、課題について紹介する。
電子サイクロトロン共鳴を利用したイオン源(ECRIS)は近年益々利用分野が広がっている.Geller以来,世界の高収量装置では経験的スケーリング則に基づいた装置作りは今や第4世代の円熟期を迎えている.しかし高周波数化と強磁場化が必要な要因や各種の現象理解は,今なお十分とは言えない状況である.本研究グループではECRISにおける多価イオンビーム生成の実験的研究過程で,計測事実を基にECR効率化や電磁波伝搬を考察し,現状の多価イオンビーム高収量化に対する問題点を指摘すると共に,新たな共鳴現象を利用する可能性があることを示した.本講演では経緯と基礎的事項の後,我々グループの展開を説明する予定である.
半導体向けイオン注入装置は、イオンソース、質量分離部、加速部、注入・搬送部の4つの主要な構成要素から成り立っており、特定のイオンを半導体基板の目的の深さに注入することで、基板内部にP型やN型の半導体を生成し電気的特性を作り出すために使用されるほか、ターゲット材料表面の改質や耐久性向上などの用途にも利用されています。特に高エネルギーイオン注入装置は、エネルギー、注入角度、ビーム発散角度など、目的の深さへ正確に注入をするために、高精度の測定・制御が必要とされます。
例として、CMOSイメージセンサのフォトダイオードやSiCパワーデバイスのSJ(スーパージャンクション)などの製造に使用されています。
放射線は現代の医療分野において診断や治療、滅菌など様々に利用されているが、中でもイオンビームは、放射性薬剤合成、放射線がん治療、医療材料製造などに用いられてきた。本特別講義ではそれらの実例を紹介するとともに、イオンビーム生成のもととなるイオン源装置に着目して、今後の技術的方向性を概観する。
理研RIBFではウランビームの大強度化に取り組み、この15年余りの間に約千倍の強度増強に成功している。ストリッパー(重イオンから多数の電子を剥ぎ取り、価数を一気に高める装置)開発は大強度化の大きな鍵であったが、我々の開発した高耐久のHeガスストリッパーは加速可能なウランビーム強度のリミットを大きく引き上げた。
策定中のRIBF将来計画ではさらに20倍の強度のウランビームが求められ、そこで中核を担う装置が荷電変換リングである。内蔵されるガスストリッパーへの要求はさらに過酷で、ウランによる電離状態がビームに与える影響も予想される。
講演では以上の話題を軸に荷電変換の基礎と今後の課題について述べる。
電子サイクロトロン共鳴イオン源における多価イオンビーム電流量の増加のための経験的手法として、軽元素ガスミキシング法がしばしば利用される。混合プラズマ中の軽元素イオンに対するイオンサイクロトロン共鳴(ICR)用の低周波数電磁波を導入することで、さらなる多価イオンビーム電流量増加の可能性が考えられている。本研究グループではXe/Ar、Xe/HeまたはAr/Heの混合プラズマを対象としてICR用低周波を導入し、イオンビーム電流量の価数分布測定とプラズマパラメータ測定、また、イオン温度に依存する物理量としてビームエミッタンス測定を行ってきた。本報告ではこれらの実験結果とその考察について述べる。
半導体製造工程におけるイオン注入には、ECRイオンビーム装置が利用されている。従来の装置は大型かつ高価であるため、本研究室では小型かつ安価で製作可能な卓上型ECRイオンビーム装置の開発を行っている。質量分離器には電磁場直交型分離器(ウィーンフィルタ : WF)を採用している。
本研究では、Arイオンビームを生成してWFで質量分離実験を行った。また、ビーム引出電圧と静電レンズ印加電圧を変化させ、ワイヤープローブによるイオンビームプロファイル測定でWFの質量分離の分解能を評価した。その結果、ビームがイオン種ごとに分離されていることがわかった。当日は詳細な実験結果について報告する。
イオン源において、ビームのエミッタンスはプラズマの状態を反映しており、ビームの輸送効率や加速効率にも強く影響する。そのため、エミッタンスはイオン源開発、加速器施設の運転の双方において非常に重要な物理量である。そこで我々は、4次元エミッタンスを高速で測定するためにペッパーポット型エミッタンスモニターの開発を進めてきた。一般的にペッパーポット型エミッタンスモニターでは、測定精度が低くなりやすい。この課題を解決するために、我々はマスクとスクリーン間の距離を可変にし、Optical Flowを用いた解析手法の開発を行った。これによりエミッタンスの測定精度を10%以上改善した。
レーザーイオン源はレーザー生成プラズマからイオンビームを引き出すイオン源でありパルス重イオンビームの形成に利用される. レーザー生成プラズマ生成時のイオン密度が高いため,レーザーイオン源は大電流密度のイオンビームを供給可能である. また, アブレーションプラズマから直接イオンをRFQ線形加速器に入射する直接プラズマ入射法(DPIS)を利用することで 10 mAを超える大電流の重イオンビームも得られる. 本発表ではそれらの技術を用いて得られたリチウムイオンビームを利用した加速器中性子源開発の取り組みを紹介する.
ムーンショット型研究開発事業目標10ではフュージョンエネルギーの実用化を目指して様々な分野で研究開発が進められる。本プログラムでは、核融合分野へ新たな加速器技術を展開させることで、フュージョンエネルギー開発にパラダイムシフトを生み出すために、革新的加速器技術の大強度化及びコンパクト化を目指す。大強度化によりアンペア級ビームの加速器技術を確立し、新たな中性子源として核融合炉材料の開発を加速する。さらに、自動サイクロトロン共鳴加速器により加速されたイオンを直接プラズマに入射・加熱することで、ビーム駆動型の小型核融合炉の成立性を検証する。本発表ではプログラムの概要について紹介する。
電子サイクロトロン共鳴(ECR)イオン源は、ECR現象のための磁場分布に加え複雑な電磁場とプラズマの相互作用を伴う装置である。COMSOL Multiphysicsは、マルチフィジックス解析を前提とした有限要素法(FEM)に基づく汎用物理シミュレーションソフトウェアであり、マイクロ波プラズマのモデル計算を行う機能を備えている。このソフトウェアを用いて、単純な体系を仮定したECRイオン源のモデリングを試みた。AC/DC、RF、プラズマの3つのモジュールを用いた連成解析結果について報告する。
電子ビーム励起プラズマ(EBEP)は大電流の電子ビームによるプラズマ発生装置である。この装置では電子の供給源であるプラズマを発生させる場合に、フィラメントを用いてLaB6を加熱し電子を供給することで、低電圧で放電を行う。イオンセンシティブプローブ(ISP)とマルチグリッドファラデーカップ(MGFC)の2つの測定機器を設置し、放電時のイオンのエネルギーを測定した。ISPは磁場中の放電においてラーマー半径の違いを利用し。電子の流入を抑えて測定を行うことができる。また,MGFCは3層(G1,G2,C)に分かれており、G1の負電圧で電子を抑制し、G2電圧変化でのC流入イオンでエネルギーを測定できる。
ダイヤモンドは絶縁破壊強度や熱伝導度など優れた物性を持つワイドバンドギャップ半導体である。本研究では、Beの放射性同位体であるBe-7の核種変換反応を利用し、Liをドープしたダイヤモンドの製作を提案する。Be-7は電子捕獲反応により安定同位体のLi-7に変換し、格子を壊すような電離放射線を発生しない。そのため、Be-7を表層にイオン注入し加熱拡散させることで、格子を欠損することなくダイヤモンド中に分布させることができれば、Be-7の壊変とともにLiが注入されたダイヤモンドとなる。発表では研究の概要と、安定同位体のBe-9を用いたコールドテスト、Be-7のイオン注入などについて報告する。
原型炉用NBI加熱では、長時間運転が可能でメンテナンスの容易な非セシウム(Cs)型負イオン源の開発が急務である。本研究室では、高密度シートプラズマを用いて非Cs型負イオン源(TPDsheet-U)の開発を推進している[1]。実験では、ガス圧力0.3Pa、引出し電圧10kVで水素負イオンビーム電流密度約8mA/cm2、随伴電子電流と負イオン電流比0.5~2.0が得られている。発表では、負イオンビームの引出し特性と大面積化用非Cs型負イオン源のプロトタイプ(TPDsheet-N)について報告する。
[1]A.Tonegawa,et al,Nucl.Fusion,61(2021)106030.
RF水素負イオン源において引き出されたビームが振動成分を持つことが観測されている。この物理において、引き出し孔に近い下流部領域におけるプラズマメニスカスに対する時間振動の影響を理解することが重要となる。特に負イオンを多く含むプラズマの場合、メニスカスのプラズマパラメータへの依存性は未だ不明である。
このメニスカスに関する物理過程を理解するための第一歩として、3D-PICコードKEIO-BFXを用いた定常シミュレーションにより、メニスカス形状の負イオンを含むプラズマ密度依存性を解析した。シミュレーションの結果、メニスカスは表面負イオンの生成量と、電子と負イオン密度の比に依存することが示唆された。
ITERのRF負イオン源開発ではビームの集束性についてまだ実証が完了していない。近年、RFが直接メニスカスに高周波振動を引き起こし、ビーム集束性を劣化させる可能性が明らかになった(K. Nagaoka, accepted to Scientific Reports)。ビーム集束特性からのこの現象をどのように理解できるか?また、この振動を抑える方法について、最新の成果を基に議論する。スクールなので、研究発表というよりは、Lecture的な講演を準備してみたい。